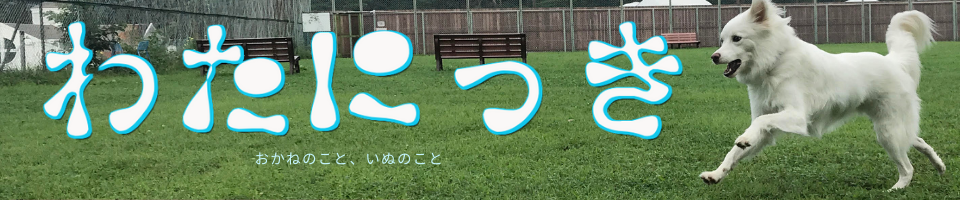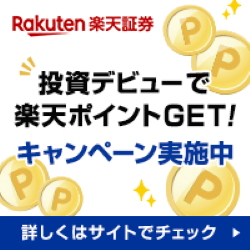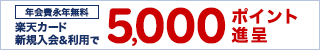銀行員や証券マンは投資行動に制限を課せられていることが一般的です。金融機関によって制限範囲は異なりますが、多くのケースでは以下に該当する取引に制限があると思います。
- 国内個別株式
- 投機的な取引(短期売買・レバレッジ取引)
多くの場合、銀行員はFX、株式投資は禁止です。
正確に言うと、株式投資については、
- インサイダー情報を持ち得る銘柄の取引は禁止
- それ以外は3か月以内の短期売買禁止・取引の都度届け出必須
この記事では、銀行員は手を出したらアウトな投資と、 銀行員でもできる投資・資産形成方法についてまとめました。
私は銀行を辞めて数年経っている身です。また、銀行によって規則が異なるので、投資する場合は最新の社則を確認してください。
銀行員が株式投資・FX取引を制限されている背景
これらの投資行動が禁止・制限されているのには理由があります。
- インサイダー取引規制
- 投機的利益の追求を目的として有価証券その他の売買を行うこと
銀行員が自由に行えない投資として、「国内個別株」「FX」にフォーカスをあててみましょう。
銀行員が国内個別株への投資が制限されている理由
株式投資については、インサイダー取引規制が背景にあります。
【インサイダー取引】
上場会社の関係者等が、その職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して、自社株等を売買することで、自己の利益を図ろうとする
JPX HP
法律ですので、もちろん銀行員でなくとも適用されます。実際に上場企業の関係者が逮捕される事件もありました。
銀行員はどうしても、さまざまな企業の内情に触れることができます。担当先に上場企業がある場合もあるでしょう。
私が銀行の支店で勤務していた時は、支店で取引している上場企業株の取引には承認が必要で、それ以外は事前の届け出をすることで取引であることが一般的です。
支店の方針によって変わりますが、実質個別株投資は禁止という暗黙のルールのもと運営されているケースが多いと思います。私が勤めていた支店もそうでした。
また、上場企業の情報に広く触れる可能性がある部署だと、オフィシャルに国内個別株投資は禁止の場合があります。
商工中金のような非上場の中小企業相手のビジネスをしている場合や、一部のネット銀行ではこの規制が緩いケースがあり、インサイダー取引に該当しなければ個別株取引も行うことが可能です。
『短期売買』については、目安は保有期間3ヵ月以内の売買は短期とみなされることが多いようです。私がいた銀行では、保有期間が3ヵ月を超える場合は、申請または届け出を行ったうえで取引可能でした。
その辺は勤め先の規則(と暗黙のルール)を確認してください。
銀行員がFXを禁止されている理由
銀行員は、投機的利益の追求が禁じられています。多くの銀行の社則には、おそらくこの文言が記載されているでしょう。『行員は専ら投機的な取引をしてはならない』。
銀行の社則における「投機的な取引」とは、レバレッジ取引と短期(3ヵ月以内)売買を主に指します。
レバレッジ取引は少ない元手で大きな資金を動かすことが出来るため、下手をすると大きな損失を抱えかねません。
お金を扱う銀行員の職業倫理として、そういった投機行動には規制が設けられています。
銀行のコンプライアンス研修で、「FXなどで大きな損失を出し、顧客の預金を不正に引き出して補填にあてた」などのビデオを見たことがある人は多いと思います。
ちなみに、銀行員でも証券口座の開設は可能です。ただし、信用取引やCFD・オプション取引の口座は開設できません。

銀行員におすすめの投資商品
投資に制限を受けている銀行員でも投資できる金融商品を大別するとこんな感じです。
- 投資信託
- 生命保険
- 外貨預金
- 制度預金
- クラウドファンディング/ソーシャルレンディング
- 仮想通貨
要するに、レバレッジ無し、かつインサイダーの可能性なしのものならOKであることが多いです。(仮想通貨はレバレッジ無しなら大丈夫だと思いますが、よく規則を確認してください)
銀行員におすすめの投資方法
さて、銀行員がすこぶる投資しにくいことがわかったところでおすすめの投資です。
投資信託(NISA、iDeCo、DC)
銀行員、とくにリテール担当なら釈迦に説法になってしまいますが、投資信託を定期購入するのがおすすめです。
NISAやiDeCoなどの制度を利用し税制のメリットを受けつつ投資しましょう。
また、会社にDC(確定拠出企業年金)があれば、一定割合をリスク資産に配分するといいと思います。給与天引きなので気づいたら資産が築けるでしょう。
投資対象は、世界株もしくは先進国・米国の株式のインデックス投信に積み立て投資をするのが鉄板かと思います(つまらない結論でスミマセン)。
若い方なら株式に全額投資して気絶してればいいと思います。リタイアが見えてきたら、良いタイミングで債券や定期預金などにスイッチするのも良いと思います。

楽天証券×楽天カード×楽天キャッシュで1.5%還元
NISA・iDeCoは取扱商品が多彩で手軽に手続きできるネット証券の利用をお勧めします。
また、以下の方法で1.5%の還元を受けることができます。
- 楽天カードから楽天キャッシュにチャージ(残高キープがおススメ)で1%
- 投資信託の買い付けに楽天キャッシュを利用で0.5%
楽天カードは単体でもポイント還元率1%、複数カード発行可能と使い勝手がよいです。私はメインで利用しています。まだお持ちでなければ上のバナーからどうぞ。
制度預金
俗にいう財形貯蓄です。福利厚生が充実している銀行では、財形預金に上乗せ金利がある場合が多いです。
給与天引きで貯蓄できるのもメリット。
私がいた銀行では、財形預金に3%の金利がついていました(上限あり)。おいしいです。私は限度額までMAXの金額を積み立てて、ストップしました。
持株会
会社の株を従業員が購入する持株会への参加もアリだと思います。一般に銀行株は高配当です。持株会に加入することで奨励金がもらえる、という制度がある場合もあります。
生命保険
初めに言っていきますが、生命保険は投資ではありません!
もし、あなたが独身(万が一、無くなっても経済的に困る人がいない)ならば、生命保険料控除の範囲内程度でいいと思います。※詳細は国税庁のHPをご参考ください
もちろん家族がいたりして、保険の本来の目的で生命保険を契約する場合は別です。
たまに保険は不要と声高らかに叫ぶ人を見かけますが、安易に影響されないでください。保険は個別性が高く、どういった保険がよいかはケースバイケースです。一概に要不要が判断できる性質の商品ではありません。
クラウドファンディング
個人から資金を募り、不動産や会社や事業に投資を行うものがクラウドファンディング(ソーシャルレンディング)です。
クラウドファンディングとソーシャルレンディングに明確な違いが定義されているのかよく分かりませんが、クラウドファンディングは他人の夢を応援するものだったり、新商品のプレマーケティングに使われており、リターンが金銭でない場合が多いです。
国内の不動産を投資対象にしたソーシャルレンディングが比較的取り組みやすいかな、と思います。こちらにまとめたので、目を通していただけると嬉しいです。

暗号通貨/仮想通貨
ハイリスクになりますが、仮想通貨は規制されていない銀行も多いのではないでしょうか。
レンディングもすることで金利収入を得ることも可能です。
私自身、ビットコインで100万円を倍にしたのが投資デビューでした。
よくよく会社の規則を確認したうえで、無理のない範囲でお楽しみください。
銀行員の投資 まとめ
NISAやiDeCoを活用しつつ投資信託で株などに投資しつつ、財形や持株会で福利厚生が充実している銀行員もメリットを活かしましょう。
物足りない方は、ソーシャルレンディングや仮想通貨などにもチャレンジしてはいかがでしょう?
おまけ 副業について
みずほ銀行など、副業を解禁している銀行も出てきました。銀行で数年働けば、それなりの専門性が身についていると思います。
スポットコンサル「ビザスク」では、自分にとっての当たり前が人の役に立ち、お金がもらえる経験ができます。
社会人なら登録しておけば、自分に合った案件を受けることがあると思います。おすすめです。