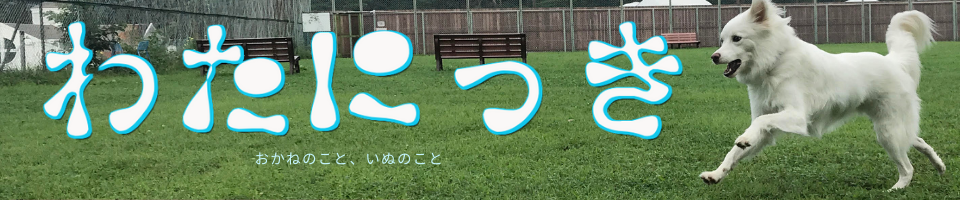税金払いたくない!!
2019年10月、消費税が上がりました。どうですか?痛いですよね・・・
でも、消費税は税金のごく一部にすぎません。所得税やらなにやらあります。
しかしサラリーマンの場合、会社が代わりに税金の処理をしてくれます。
そのため、自分が税金を払っている認識すらせずに生きている人が結構いるんじゃないでしょうか?
あなたは、自分が年間いくらの税金を払っているのか認識ありますか?
認識しなくても、所得税の負担って結構大きいです。給与明細を見るとわかると思います。
今回は、私が実際に行った節税術についてまとめます!
会社を作って経費を使おうとか、不動産を買って償却を取ろうみたいな話ではなく、だれでも出来る方法だけです!
所得税に仕組みについてざっくり説明します
「そんなこと知ってるわ!」って人は読み飛ばしてくださいね。
所得税とは、その年の「稼いだお金」(=所得)に対して課せられる税金です。
所得税は、累進課税といって所得が増えるほど税率が上がります。
例えば「課税所得」が330万円~695万円の人だと20%の所得税がかかります。
所得が4,000万円を超えると、所得税率は45%になります!

所得税の計算式は、「所得×税率ー控除額」です。
「所得」とは、給与収入(いわゆる額面)から「様々な控除」を差し引いた金額です。
税金を計算するときにもとになるのは、「課税所得」です。
今回ご紹介するのは、その課税所得を減らすことができる「様々な控除」についてです。
所得控除金額×あなたの所得税率=お得になる金額ということです!
イメージが湧かない方へ具体例
(例)年収400万円の場合
控除なし
400万円-0円=400万円(課税所得)
400万円×20%-427,500円(基礎控除)=372,500円
100万円の所得控除がある場合
400万円-100万円=300万円(課税所得)
300万円×10%-97,500円=202,500円
なんと、372,500円‐202,500円=17万円も税金が減ります!
所得控除できる制度を活用し、確定申告や年末調整をすることで税金の還付を受けることができます。
何もしなくても受けられる控除
- 基礎控除
- 配偶者控除
普通のサラリーマンでも利用しやすい所得控除
ここからが本題。普通の若手サラリーマンでも活用できる所得控除です。
医療費控除
一年間で、自分と家族の医療費から10万円を差し引いた金額が控除されます。
言い換えると、10万円未満の場合は申告しても無意味です。
私は歯の矯正をしたのですが、保険適用外で100万円近くかかりました。
あとは、妻の出産費用の自己負担分や風邪をひいたときの診察代・薬代が対象になりました。
医者にかかったら領収書は保存しておきましょう。薬局で薬を買ったりした場合も含まれます。
もし金額が大きくなるようであれば、確定申告すれば払いすぎた税金が返ってくるかもしれません。
個人版確定拠出年金(iDeCo)
2017年1月から、一般企業に勤めているサラリーマンも加入できるようになりました。
確定拠出年金で、会社が拠出できるのは年間33万円です。
iDeCoは、その33万円と会社が払う掛金の差額分を拠出できます。
その全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象になります。
私の場合は、年間144,000円でした。
iDeCoで拠出したお金は任意の投資先へ投資することになります。
その場合の運用益も非課税です。
元本保証じゃないとヤダ!という方は、全額定期預金に投資すれば所得控除のメリットだけ受けることができます。
ですが、個人的にはせっかくなら運用に回すことをおすすめします。
長期×積み立てという投資の勝ちパターンを再現できるからです。
2020年1月時点では、iDeCoに加入するには会社の許可が必要ですが、それが不要になる方向で改正案が検討されています。
ふるさと納税
寄付金控除に該当します。
聞いたことあるけどよくわからんからやっとらん!という人のために仕組みを説明するとこんな感じ。
- 地方の自治体に寄付を行う
- 寄付した金額は寄付金控除の対象(金額は所得が多いほど大きい)
- 自治体からは寄付のお礼として、地元の特産品などがもらえる
勘違いしがちなのは、あくまで寄付であって、特産品を購入してるわけではないこと。
「一万円も出すのに返礼品しょぼくない?」とかいう人がいますけど、目的はあくまで控除。
返礼品はオマケにすぎません。
どうせ払う税金なら、何かしらお礼を頂けるならそのほうがいいでしょ?
所得によって控除できる上限が決まっているので、「ふるさとチョイス」「さとふる」などでシミュレーションしてみましょう。
生命保険控除
民間の生命保険(日本生命、明治安田生命、ソニー生命、プルデンシャル生命保険などなど)の保険料を控除できる制度です。
下記保険について、それぞれ40,000円まで、計120,000円まで控除が受けられます。
・一般生命保険(主に死亡保険)
・介護医療保険(主に医療保険やがん保険)
・個人年金保険(個人年金のみ)
毎年10月くらいに生命保険会社から書類が送られてくるので、それを保管しておきましょう。
生命保険料控除は、会社の年末調整で申請すれば確定申告しなくてもOKです。
4.株式の譲渡損失
株式投資をしている方で、損失が出てしまった場合は確定申告によって還付もしくは3年間の繰り越しが可能です。
私は株式投資はしていないので、詳しくは調べてください(汗
(番外) NISA、積立NISA
所得控除ではありませんが、節税という観点では、NISAを活用した運用もおすすめです。
通常、投資信託や株式の値上がり益には20%程度の税金がかかりますが、この制度を活用すると非課税になります。
例えば、100万円投資して、200万円になった場合に、
【NISAなしの場合】
200万円‐100万円=100万円(利益)
100万円×20.315%=約20万円の税金がかかります!
NISAを利用するとこの税金がナシになるということです!
NISAの投資可能額には年間120万円、投資してから5年間という制限があります。
積立NISAはNISAの毎月積み立てバージョンです。
年間40万円、期間20年という制限があります。
銀行や証券会社でNISA口座を作れば利用可能です。
株式投資をしたい人は証券会社で開きましょう。
まとめ
1.医療費控除
2.iDeCo
3.ふるさと農材
4.株式損失申告
5.NISA、積立NISA
以上、おススメ節税術でした!ではまた!ー